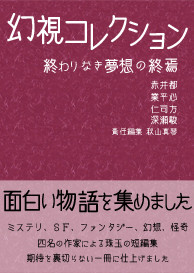川獺右端「魔女を火あぶりにしないために」
フランツ親方は魔女の腰紐を引いて、処刑場に入っていった。
魔女は若い貴族の娘で、あちこちに酷いあざがあり、顔が腫れ、片目がふさがりかけていた。
足を引きずるように歩いている事から、伸ばし台の拷問に掛けられたのだな、と、フランツ親方には解った。
拷問にフランツ親方は立ち会わない。事件の拷問は警使の役目であるし、魔女の拷問は最近作られた査問委員会の仕事なので、関わらない。
首切り役人たるフランツ親方の仕事は、処刑によって咎人に罪を贖わせる事で、捜査ではない。あまりに酷い冤罪の疑いがある場合は、処刑人の誇りにかけて、刑場から差し戻す事も出来るが、担当した役人の面子がつぶれるので積極的には行使しない。
魔女裁判にいたっては、魔女であるのか、そうで無いのかは、宗教家では無いフランツ親方には解らない事だ。
広場には沢山の人々が集まっていた。
熱狂的というよりは、困惑しているようなそんな雰囲気だった。
ニュルンベルグで魔女が火あぶりにされるのは初めてだからだろう。他の都市だったら罵声や石が飛んできている所だ。
娘が軽い咳をして、顔をあげて、フランツ親方の目を見た。
「わたし……。魔女じゃ無いんです」
娘に小声でささやかれたが、フランツ親方は歩みを止めなかった。
「審問の差し戻し、も出来ますよ」
「……いえ、再審問は……、体がもたないと思います」
「そうですか」
「ごめんなさい、ただ、親方に、だけ知っておいて欲しいと、そう、思ったのです」
娘はそう言うとはにかむように笑った。
彼女の名をフランツ親方は知っていた。ヴィラという中堅貴族の娘だった。城の近くを明るく笑いながら歩く彼女を見かけた事がある。今は疲れ、うちひしがれ、手かせを重そうにして歩く彼女だったが、明るい金髪の色だけが、その時と同じに明るく綺麗だった。
「審問官の方が……、仲間の事を吐けと……、すごく責められました」
ヴィラは立ち止まった、そして誇らしげに少し胸を張った。
「でも、言いませんでした、こんな事は私の所で終わらせるべきで、お父様やお母様を巻き込むべきじゃありませんもの」
フランツ親方はヴィラの澄んだ瞳を見つめ、うなずいた。
「また審問されたら……、今度こそ、誰かを巻きぞえにしてしまうと思うのです。なので、親方の手を煩わせてしまいます」
二人はゆっくりと歩き出した。
柴が積まれた火刑台が近づいてくる。
「それだけはごめんなさい」
フランツ親方は、どう声を掛けて良いかわからない。
不正義があった、罪も無い娘が魔女として焼かれようとしている。
処刑人の名において再審を求める事は出来る。だが、それをしたところでヴィラは審問中に死ぬだろう。屈辱にまみれ、これまで守ってきた大事な物を失い、土に帰ってしまう。
――こんな事は私の所で終わらせるべき。
と彼女は言った。親方もそう思った。
親方はヴィラを柱にくくりつける。司祭が長い十字架で彼女の頭をなでながら、祈りの言葉を贈る。
柴をヴィラの近くへ置いていく。
「相談があります」
小声でフランツ親方が言うと、ヴィラは小さくうなずいた。
「苦しまずに死ぬ方法があります。首筋の動脈を切れば、苦痛無く眠るように死ねます」
どうしますか、と親方は目でヴィラに返答をうながした。
「ごめいわくでは……」
「問題はありません」
「お願い、します……」
フランツ親方はうなずくと、柴を置くふりをして手の平に隠した小さなナイフでヴィラの首をかききった。傷を背中まで伸ばして、周りに血が見えないようにした。
「だんだんと意識が薄れます。あなたに神のご加護がありますように」
「ありがとう……ございます」
ヴィラは親方に向けて微笑んだ。
司祭の手によって、柴に火が掛けられた。しばらくして火は轟々と燃えさかり、ヴィラに襲いかかった。
肌を火が焼く頃には、もう、彼女の息は無かった。
悲鳴や恐怖のもがきを見たがっていた民衆は、あっけなく焼けていく娘をみて、少し落胆した。
「ああ、火が回る前に恐怖で死んだんだな。神は慈悲深い」
野次馬が首をたれ、十字を切った。
フランツ親方だけが、燃えていくヴィラをじっと見ていた。
――こんな事は私の所で終わらせるべき。
その言葉だけが、何時までもフランツ親方の胸の奥でぐるぐると回っているかのようだった。
猿川西瓜「私のマキナ」
私の――私だけのデウス・エクス・マキナ。私の見ている世界を導いてくれる。
一本だけの枯れ木。たくさんの朽ちたロープがぶら下がっている。何の木だか、わからない。マキナが言えばその名の木になる。陽が、私の肌を焼く。日焼けはしない。赤く腫れて、水膨れして、少し膿んで、また白く戻る。
私はマキナとつながったまま、二人で肩を並べて、枯れ木の根元に座っていた。私達は千年程前に滅んだ王宮の庭の片隅にいて、上空には時折、大きな鳥の翼を持った生物が自由に舞っている。群生する蓮の池では、永久機関のセキュリティが、ボトンボトンと不規則に音をたてて、未だ侵入者から王を守っている。
私はマキナとどんな風につながっている? わからなかった。ただ、マキナとある夢を楽しんでいた。マキナと夢を見ているということは、きっと心がつながっているに違いなかった。
「いつもいつも、たいへんですね」
マキナは私の頭を撫でてくれた。
「たいへんなの。いつもいつも、私は忙しくて、することがたくさんあって、どうしようもないの」
「でも、あなたは――をしなければならない。すべての――のために」
マキナはいつも同じことを言った。私はマキナが人工知能であるのか、神様なのか、人間なのかわからない。ただ、お風呂に入らなくても、何も食べなくてもよかった。
「――のために? じゃあ夢を見ようよ」
私は、私だけが満たされていればよかった。誰にも迷惑をかけないし、そもそも「誰」がいない……。
私はマキナの髪を撫でた。陽に照らされて、暖かかった。夏の始まりの一番好きな季節に、どうして――のためにとか考えないといけないのか。それよりも、私はマキナとの今この時間を大切に守り続けたい……。
マキナは聖母という言葉が陳腐になるほど、綺麗な存在だった。マキナの与えてくれる夢を、つながりの中で感じられればいい。マキナと一緒に暮らすことの出来る最低限のお金さえあればいい。こうやって二人でずっと座り続けて、老いて、腐り、溶けて、土に還りたい。
「休みはもう、終わりでしょうに」
マキナは立ち上がり、つながりを断った。私の頭の中に、ザーッと風が吹いた音がした。草を凪ぐような音もした。
私は、「もうちょっと、マキナとつながっていたい」と、肩を落とした。
マキナは「行ってらっしゃい」と微笑んだ。
「マキナ。帰ってきたら、すぐにつながろうね」
私はいつも言う。マキナはいつも頷く。
崩れた王宮の中に入って仕事着に着替えた。どれだけ蔦や埃で風化しても、大理石に刻まれた剣や弓のへこみの痕は相変わらずだった。王宮の門まで来ると、階段が下界へと続いている。いつもここでマキナに見送ってもらう。
「あら」
私が働きに行こうとする途中、マキナは空を指さした。
「ほら、今日もまた、飛んでますね……」
マキナは彼らに手を振った。
「ダメ! ゴミ屑に挨拶しちゃ」
マキナは微笑んだまま「なぜ? どうして」と言った。
「あいつらはね、人間であることを捨てた、捨てる身分にあった、捨てたい気持ちに逃げた、最低のクズなのよ。臆病者のくせに、私達を見下ろして、馬鹿にすることを囁いているの。人の話を聞かないあいつらの汚物は全部私達に降り注ぐのに、彼らは内心であざ笑っている。多分……いや、絶対そうに決まってる! 翼の生えた動物に成り果てた人は、マキナを汚すことしか考えないよ。関心を持っちゃダメ」
「そう……」
私が「失せろ!」と、叫ぶと、翼の民は階段の上空から離れて、王宮の屋根を越え、森の向こうにある巨大な塔の方へ去って行った。
私はマキナの手を握って、引っ張った。額と額をくっつけて、「あなたは……マキナ……誰にも渡さない……」と小さく呟いた。
マキナは「はーい」とおおらかに笑った。
階段で幾度も振り返りながら、私は下界の都市へと働きに出かけた。
そして、陽が暮れた頃に帰ってきたら、マキナの姿は消えていた。
蓮の池はなぜか涸れていた。セキュリティがめちゃくちゃに壊されていたが、マキナを守るために作動した形跡はなかった。名も知らぬ枯れ木だけは名も知らぬ赤い花をつけて満開になっていた。「綺麗……」と思って近付くと私達が座っていた所に大量の糞尿が落ちていた。その糞は、下界に続く階段へではなく、反対の方向に落ちていっていた。森の中へと点々と続き、その先の塔へ……。
添田健一「鳳翔太白山祈雨縁起」
鳳翔府に着いたのは十二月十四日。職名は鳳翔府簽判(せんぱん)、知府の次官にあたる地位である。令名のほまれ高い蘇軾は蘇賢良と呼びならわされ、鳳翔の官吏やひとびとににぎにぎしく迎えいれられた。
このときの鳳翔の知府であり、蘇軾の上官にあたる宋選(そうせん)は、蘇家とも古くからのつきあいのある家柄であった。温和な人柄であり、四十代の半ばを過ぎた恰幅のよい人物であった。宋知府はにこやかに受けいれてくれた。
「まずは着任のあいさつもかねて府の孔子廟にお参りをなさい。今年ももう終わりです。正式なつとめに就くのは年が明けてからでもいいでしょう。お参りのあとはゆっくりあたりの景勝や文物を見てまわり、寺社にも詣でるといい。そうして鳳翔府のひとびとと親しみ、早くなれることです」
「ご配慮ありがとうございます。なによりものことばです」拱手する。はじめての任官で上官にもめぐまれたことをうれしく思った。
翌翌、十六日、彼は孔子廟を訪れた。
鳳翔は戦国の世に秦国の都にもなった古都である。黄土のひろがる一帯には黄河の支流である渭(い)水(すい)が流れている。この渭水の流域こそ、この国のいにしえの文化をはぐくんだ揺籃の地であった。あたりは天を突くがごとき高山に囲まれており、峻厳なる稜線は巨大な蛇が横たわっているかのごとしであった。
鳳翔府より南を向き、東から西へと目を移せば、西に向かうほど山のつらなりは高みをましてゆく。西につながる大巴山脈とのあいだには漢中の地がいだかれている。はても知れぬ西方のけわしき高嶺のかさなりは、人知のおよばぬところであり、まさしく神の鎮座する威容をそなえていた。
長安から西に二百里(約百キロ)、交通の要所として鳳翔は知られる。長安が京師とされた世には西の護りの軍都としてはたらいた。西には隴(ろう)関(かん)がそびえたち、その先が隴西である。南は大散関から四川、名高い蜀の桟道と呼ばれる細い道が伸びている。
屹立した高山に囲まれた天然の要塞たる鳳翔は軍事をもって史に名を残す。後漢の終わり、いわゆる三国の世のはじまりにおいて、魏はこの鳳翔を兵站地としておき、北上してくる蜀の軍勢を食いとめつづけた。唐の世では、安(あん)禄(ろく)山(ざん)の叛乱により京師長安を追われた玄宗のあとを継いだ粛宗は、この鳳翔の地を足がかりにして長安奪還をなしとげた。
宋の世となってからも、強大な隣国である西(せい)夏(か)との要衝の地となっている。
古都ゆえに史跡や文物も多い。孔子廟を訪れた蘇軾を迎えたのは鼓のかたちをした十個の石であった。それぞれの石には曲がりくねった文字が彫りこまれている。石鼓である。
詩人としての感性がはたらき、身を乗りだしてこの石鼓を見つめる。師である欧陽修の著述により、これらが発見されたいきさつや彫られた文字のあらわすところは前もって知っている。はるかいにしえの周の宣王のときより伝えられる文物である。
欧陽修におのれを推挙してくれた文人である梅(ばい)堯臣(ぎょうしん)もこの石鼓を古詩に詠じている。
ところどころ摩滅した文字を追ってみる。ひびや破損により全体の半分も読めない。もとより、文字もときの移り変わりによって、いにしえとこのときでは、かたちもあらわすものも大きく異なっており、見当もつかない。
それでもかすかに読みとれる一文を右手のひとさし指で左手になぞり写してみる。十文字のうち、ひとつわかるかどうかだ。軽く笑う。これでは判読などとても望めない。
この石鼓が孔子廟におさめられたのは唐の世であり、およそ二百五十年ほど前である。それまでは野にさらされていたのだという。周の宣王の世といえば、かれこれ千九百年のときを隔てている。さても昔の文物が剥落をすすませながらも、なおも文字としてのかたちを残しつつ廟におさめられているのだ。
千九百年。思いを馳せずにはいられない。それだけの年月にこの国ではいかほどの王朝の興亡と変転があったであろうか。十個の石鼓は同じときの流れのうちにひっそり息をつないできたのである。ひとの富みさかえるさまなど、この石鼓とくらべたら一朝に過ぎない。胸の奥底から嘆息をつく。ひとの生とはなんとはかないものであろうか。
鳳翔にはこの石鼓をふくめて八観と呼ばれる名所がある。宋知府のありがたいことばに甘えて、この機にそれらを見てまわることにした。
いにしえの飲凰湖こといまの東湖の水辺を散策し、李氏園にて詩を作り、真興寺の仏閣を詣で、秦の穆(ぼく)公墓を訪れた。穆公の娘が簫(しょう)を吹くと鳳凰が飛んできて、この地に舞い降りたといういい伝えこそ、鳳翔の由来である。
天柱寺にて、唐代の著名な彫刻家楊(よう)恵之(けいし)の維摩像の研ぎ澄まされた品のよい顔立ちと法衣の襞の精巧ぶりに感嘆をおぼえた。
開元寺では古碑である詛(しょ)楚(そ)文を観覧した。同寺の東塔では、王(おう)維(い)と呉(ご)道子(どうし)の描いた竹と仏像画に拝する栄にも浴した。王維は唐の高官で詩人として知られるが、詩のみならず、画にも書にも楽にも長じていた。呉道玄こと呉道子は、画聖とも呼ばれ、その奔放たる大胆な画法から、「山水画の変は呉道子にはじまる」と称されるほどに画風の新しきを切りひらいた人物である。
壁画の前で立ちつくす。かねてより望んでいた呉道子の実物を目にするのははじめてである。筆づかいは雄放でありながら全体をとらえたときには調和をなしていた。自由でありながら自然。これこそが若き蘇軾が胸に描く美の極致であった。
ときも忘れて動かぬままでいると、寺院の年かさの僧侶が声をかけてくれた。呉道子についてあれこれと教えてくれる。話は尽きることなく、その日は開元寺に泊まった。食膳も整えてくれ、特産のめずらしい果実をふるまわれた。僧侶は帰りぎわの見送りがてらに、いつでもまたおいでなさい、とにこやかに申しでてくれた。
空木春宵「Wish You Were Here」
「アーキテクトじゃないよ。アーキテクスト」
若い女性事務員が三度、僕の肩書きを言い誤ったとき、僕はカウンター越しにそう訂正した。けれども、彼女は上目遣いで僕に頷いてみせながら、ええ、そうです、ミューズ・エンジニア・アーキテクトのニナガワ様ですと、またも繰り返す。黒髪に縁取られた顔は均整が取れているし、体内のMUSEを介して見えない相手と話している姿は詩でも諳んじているようで、正に詩神(ミューズ)といった感じがするけれど、続く言葉は入国審査官が口にするのと同じくらい無粋で無愛想なものだった。
「アポイントメントの確認が取れました。お手数ですが、DNAパスをご提示ください」
言われるがまま、視界の内に表示されたコンソールを操作し、パス用のアプリを起動した。MUSEのポートを開き、国際保証会社から発行された本人確認用のコードを、目の前に居る相手のMUSEに転送する。
事務員は白い手を宙にひらめかせ、僕の目には見えない―可視設定が共有されていない―コンソールに指を這わせた。動きに合わせて制服の袖口で揺れるブレスレットは、貼り付けられたテクスチャの模様(パターン)が派手過ぎて、事務員という職にふさわしい抑制を欠いている。一口に言えば、下品。複雑に絡み合った蔓薔薇の模様からは甘い香が立ち上り、〝性的な感情〟を僕の中から引き出そうとしたが、僕はそいつを軽くあしらった。この程度のオモチャに振り回されていたら、同業の連中に笑われる。
「パスの照合が完了いたしました。では、MUSEカードをお外しの上、ゲートをおくぐりください」
「何だって?」思わず、頓狂な声で聞き返した。「カードを、外せと、そう言ったのかい?」
「ええ。当〈領区〉―〈ドメーヌ・ド・マ・メール・ロワ〉では、ご来訪された全ての皆様に我々が用意したカードへの換装をお願いしております」言いながら、彼女はカウンターの下から一枚のカードを取り出した。拵え物の笑みをにっこりと顔に浮かべ、ゲートの向う側の卓上にそれを載せる。「ご滞在中、ニナガワ様のカードは私どもが丁重に保管致します」
「困ったな」僕は自分の首筋を指先で叩きつつ、「仕事柄、こいつに詰まってるデータが必要なんだけど。僕のクライアントも、この事は諒解してる?」
勿論ですと彼女は答えた。当〈領区〉の規則ですから、と。僕が大仰に肩を竦めてみせたところで、そのかんばせに貼り付いた笑顔のテクスチャは僅かばかりも揺らぎはしない。不承不承ながらもコンソールをいじり、MUSEをシャットダウンした。まあ、いい。カードを換装したら、クラウド上のストレージから各種データと環境設定用のファイルをすぐに落とそう。最低限の作業環境はそれで構築できる。
途端、天井や壁、カウンターからソファまで、ロビーの景色を構成するあらゆる物から質感と柄―テクスチャ―が取り払われ、セラミック製の素地が剥き出しになる。事務員の制服は布地の綾をなくして、艶やかな光沢を放つラテックスのボディスーツへ、手首で揺れるブレスレットも手錠のように素っ気ない金属の輪へと早変わり。白い顔を飾るやや古風なメイクは―どうやら本物らしい。
うなじの半生体スロットから排出されたMUSEカードを手渡し、僕はゲートをくぐった。引き換えに受け取ったカードを挿入すると、親指の爪くらいに小さなそいつは、頭の奥―視床下部までするりと呑み込まれていった。視界の片隅にパルナッソス社のクレジットと、続けて、九柱の女神をあしらったロゴが浮かんでは消える。
「ツバキ・メールロワのオフィスまではオートポッドでお送りします」
事務員の案内を聞き流しながら、僕は起動したMUSEの設定を早速いじる。
クラウド上のストレージに接続しようとして驚いた。何しろ、接続先として用意されているのが、ローカルエリア・ネットワークだけだったから。どういう事かと訝りつつも、ひとまずそいつに繋ぎ、提示されたメニューから、アーキテクスチャ・パッケージ―呆れた事に、一つきりしか用意されていない―を選択し、展開する。魔法の杖の一振りだ。無機質で殺風景だったロビーは、木製の床と石壁からなる空間へと見る見る内に様変わり。磨き抜かれて艶光りするカウンターの木理からは、心地良い木の香りが立ち昇り、和やかなムードがふんわりと頭の中に広がる。
それから二、三の手続きが済むと、僕はようやく〈領区〉へと足を踏み入れる事を許された。立ち去り際、事務員は胸の前でブレスレットをわざと揺するようにして手を振り、ウィンクを寄越した。彼女には悪いけれど、それよりも僕の目を引いたのは、彼女の左のまなじり近くにある、ほくろだ。均整が取れていながらも無個性な顔立ちの中、そのほくろだけは強い存在感を放っていた。往年の舞台女優の姿が、脳裡に浮かんで、消える。あの女優の泣きぼくろも、彼女にとって唯一の個性と言われていたっけ。
ジャスミンの彫刻があしらわれた入領管理局のドアの向こうで僕を待っていたのは、パブリックドメインの絵本から飛び出してきたかのような、古めかしい景観だった。赤や緑や群青色のいらかを頭に被った煉瓦造りの建物が肩を並べて朝陽を浴び、整然と立ち並んだガス燈と樹々が石の敷かれた街路へ等間隔に影を引いている。石と木と鉄で出来た街並み。本物を見た事もないのに〈郷愁〉が掻き立てられる。勿論、それは文化的遺伝子(ミーム)なんていうご大層な物の産物ではなく、どこかの誰かがコーディングし、アーキテクスチャに埋め込んだ〈エモ〉によって惹起されたに過ぎない。