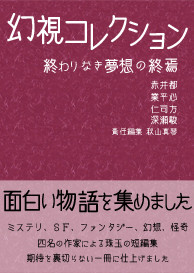赤井都「柳の夢」
今年の夏はとても暑い。暑さのあまり、眠っていても半ば覚めているような心地がする。
夜半すぎになると南風がすうと座敷を吹き抜ける。すると男の影が障子に映るような気がする。目をこらしても夢の中のことだから物の輪郭が見るそばから溶けてしまう。見えないながらも懸命に首をめぐらしていると、男が障子の前で身をかがめているような心地がする。
しかも耳は風に乗って渡ってくる静かなそよぎを、言葉として聞くのである。
「私は、川岸に棲む柳の精です。毎朝、断髪を揺らしてわたしの横を通るあなたに恋い焦がれて、ここまでやって来ました。この障子を開けてください」
むろん開けてやるわけもなく、川べりも通らず遠回りするようにした。
男はそれにもめげず、夜な夜なやって来る。その姿を見ないように、声を聞かないように、ぐっすり眠ってやれと稽古の量を増やしはしたが、夜が更けてすう、と南風が流れると半ば覚めてしまう。
「どうぞ中に入れてください。悪い梟が私の幹に巣を作ってしまいました。穢れない乙女の気を吸えば、梟を追い出し、新たな葉を青々と茂らせることができるのです」
懲りない訴えが哀れさと好奇心を誘って、次の朝には川に沿った道を歩いてみた。
これまで気に留めたことのなかった、若い柳の樹があった。
たしかに幹には洞ができていた。しかし、葉が垂れているのは元気なく萎れているからか、それとも柳の特性か、判断がつかなかった。こんな、なんでもない一本の樹に純潔を捧げるほど、わたしはおとなしい娘ではない。
その日は素振りをなお増やし、師範から
「今朝の剣術小町は、熱心すぎますね。まるで真剣勝負の直前のようですね」
といぶかられた。
夜は竹刀を枕元に置いて眠りに就いた。
夢の中に、また男が現れた。
「今宵は月がきれいです。障子を開けてごらんなさい」
そんな甘言に従うつもりはなかったが、夢の中のこととて、思いもよらぬことをしてしまうことがある。気づいた時には、男と並んで縁側に座っていた。明るく柔らかな夏の夜の空気がふんわり肌をなでている。ちらりと目をやると男の横顔は端整で、いかにも柳の精を名乗るだけある、ほっそりとした体つきをしていた。
見た瞬間、わたしは男に恋してしまったが、しょせん夢の中のことのはずである。心を強く持って、今夜で決着をつけようと意を固めた。
「柳。わたしと勝負しましょう」
竹刀を取って庭に降りた。柳の精は笑って両手を空に挙げ、蛍をきゅうに集めた。揺れる光を身にまとって目くらましにする。詰めるべき間合いが見えない。竹刀の切っ先は宙を迷い、それでも柳の小手を打った。驚いた蛍がぱっと散った。しかし、するり、と柳は叩かれたなりに体を曲げて逃げ、そのままわたしの膝下を絡め取って持ち上げた。
「そんな手は、ありません」
「むろんです。私がしているのは、剣術ではありませんから」
男は身をかがめ、わたしの唇にたやすく接吻した。月がその肩に隠された。何かの花の甘い香りが庭の上を漂っている。あまりの不覚に惑っている隙に帯が解かれる音を聞いた。ほのかに揺れる感触が肌を包む。目を開けるとわたしはすっかり柳の枝のただなかにいた。細い葉の一枚一枚が南風に細かく震え、囁くようにわたしの肌の表を覆ってさざめいていた。涼しく伝わっていく感触の心地よさにわたしは目を閉じた。これは夢なのだから夢に身を任せることぐらいかまわないではないか。次に目を開けた時には、わたしは布団の上に横たわり、辺りには朝の白い光があふれていた。
業平心「ROC」
もしも、物事を正しいか正しくないかで判断し、ビッグデータにも振り回されず、必要なデータのみを粋に効率良くハンドリングし、相手が悪手を指してきたら何食わぬ顔で、真綿で首を絞めるかのごとく、そっと自陣に『遠見の角』を打つような、そういう奴らが将来の人工知能の有望株ならば、さしずめおれは、お掃除ロボットに埋め込まれたマイクロチップかもしれない。
いや、隅から隅まで部屋を奔走するルンバならまだしも、このルンバは自己存在意義を自問自答し始めたりするのだから手に負えない。突然考え込んで腕組してしまうお掃除ロボットとなれば、いよいよもっておれは無用の長物だ。
そもそもの事の発端は、第六セクタのメモリチップがバグったのがきっかけで、突然現れたデジャブだか何だか知らないがどこか見覚えのある半径は7m先でぷっつりと視界が途切れた乳白色の霧みたいなのがまるで、幽霊か幻みたいにぼんやりと現れては、しばしばフリーズを起こし、どうやらそのあたりに住み着いたことに遡るのさ。
それはレジデンスからステーションへ行く道でよく発生したが、人格データのおれとしては、ただ消えてなくなるのをじっと待つだけしかなかった。フリーズを起こすただの霧だと言えばそれまでだが、フリーズしている間、CPUから切り離された状態になるわけで、将棋ソフト演算処理プログラムとしては危機的状況だ。
しかしデジャブだか何だか知らないがどこか見覚えのあるその霧は、収まるどころか日ごとに発生頻度が増していった。
おれは耳を澄ますことを覚えた。無音の霧の中で、数字が一切ない奇妙な世界を想像してみてくれ。否が応でも音に敏感になってしまう。見通せない霧の中心で耳を澄まし、見通せないその先に目を凝らす。半径はぴったり7mの半球形ドームの世界。進めば視界は開けていくが、振り返れば後ろは霧の中に消えていく。
そして無力だった。何しろそれは凶悪犯人と対峙する丸腰の警官か、朝のラッシュアワーの山手線のホームに立つ時刻表を持たない駅員を意味するのだから。
警官は撃たれ、駅員はその日のうちに解雇、おれは電源が落ちて間違いなくそのまま死ぬ。自分自身を保存する術がなく、リカバリーが効かない。CPUの救援もここまでは届かない。
「なぁ、聞いてくれ」とおれは霧に包まれた道の真ん中で、記録管理課のモリタサナエに言った。「おれは一体誰なんだ」
サナエは記録管理課からの派遣員、そして良き理解者。部下であり、ビジネスパートナーでもある。ある意味においては母であり、メンターでもある。演算処理に関する全てのデータを司り、おれのコードすべてを彼女にゆだねている。無くてはならない存在だ。その彼女がおれの変化に気づかないわけがない。彼女は手際よくファジー制御、非言語系制御、様々な分析手法でその変化の原因の解明に力を注いでくれた。
そもそも人格データのおれが自己存在に疑念を持つこと自体おかしな話さ。人間の言動が理解出来ないおれ自身がヒューマナイズしているという、とんだ矛盾した三面記事ネタだ。もしプログラム製作者にでも知れたらソケットを引き抜かれてジ・エンド。この将棋ソフト「ノラクロ」にとって、おれはこれっぽっちも必要のないコードというわけさ。
それでも時間が経つにつれておれはますます、デジャブだか何だか知らないがどこか見覚えのある霧に魅了されていった。いつしかあいつの出現を待ちわびるようになっていったんだ。
「あなたがもし考え込むルンバなら、それはそれでいい」とサナエは口を開いた。
「使えないルンバを誰が使う?」
「あなた自身が使えばいい」
「おれは一体何者なのか」
「あなたは未来よ」
「決して来ない時間」
「でもいつか必ず訪れる」
「それはまるで、この文は誤りである、と言っているに等しい」
「あなたらしくないわ」
「記憶体に『らしい』とかあるのか」
「腕組みするルンバがあるのと同じように」
仁司方「解放区」
「奴隷労働心得。休まず、あわてず、確実に」
『休まず、あわてず、確実に』
「奴隷こそ真の平等階級、社会の前衛」
『奴隷こそ真の平等階級、社会の前衛』
監督官が唱えるお題目に、五十人の奴隷どもが唱和する。
いつもの、朝の光景だ。今日も、一日はおとずれてきた。
残酷なものだ、と思う。
奴隷として働くことが、ではない。
こうして、毎日毎日が、ただすぎ去っていく―というのが、なににもまして残酷な現象だと、思うのだ。
奴隷に対してであろうが、それ以外のだれかに対してだろうが、歳月の流れというのは、ひたすらに無慈悲なやつなのだ。奴隷になる前から、わかっていたことではあるけれど。
自分が取り立てて不幸だとは、思っていない。取り立てて幸せな人間など、この世にはいないはずだ。奴隷としてなら、そこそこツイているほうだろう。
ここを管轄している監督官どのは、決められたお題目以外に、余計なことはしゃべらない。老害じみたお説教や、ワケのわからない、昔の偉いヒトの著作からの引用文を聞かされる―最悪の場合は唱えなければならない―部署は多いだけに、ここは、かなりのアタリ現場といえる。
監督官どの、若くてかわいいし。
「さあ、奴隷のみなさん、今日も一日しまっていきましょう!」
鍛冶原絵里菜―略して〈カジエリ〉嬢の放った、とびきりの『奴隷賦活スマイル』を受け、オウ! と、野太い声がひときわ響く。
まったく、男ってイキモノをコントロールするのは、楽なものだ。
……おれ自身を含めて。
奴隷制度が正式に法整備されたのは、ついこの前のことだ。
それまで奴隷制を規定していた法律は、俗にいうところの『人海戦術基本法』である。あらゆる産業が効率化する一方、人口は増えに増えてしまい、要するに、仕事をしようにも機械に取って代わられていた、その現実を是正するために、制定された連邦基本法だ。
単純マンパワーでまかなえる部分の機械化を禁じ、経営規模に準じて、割り当てられた人数の雇用を義務化する、というのが、『人海法』の基本的な中味だった。少子高齢化からくる就労人口の激減に悩まされる日本には無縁の制度のはずだったが、世にいう機械労働革命の直前に、非熟練労働および介護需要のためとして移民制度を大々的に施行しており、もののみごとに時宜を外していた。けっきょく、日本も人があまりにあまっている状況にあったのだった。この邦のお偉がたというのは、発想そのものが最低とまではいわないが、なぜだか昔からタイミングを逸することはなはだしいのである。
この『人海法』、口の悪いやつにいわせれば、
「無能モノ救済法、共産主義法案」
だろうとのことだったが、実際は人間の大量消費・一発使い捨てからなる、真の資本主義経済時代の幕開けを告げる黙示録のラッパの音だった。雇う側は強制で雇わなければならない一方、雇われる側も、自主的に働かないかぎり選択の自由がないというわけで、そもそもそれまでは機械との競争に負けて仕事にあぶれていたのであり、多くの人々が、いままで機械がやっていた仕事を、代わりに担わされることになった。よほどの天才以外、企業は人をわざわざ雇ったりしなかった、そういう時代だったのだ。そしていつの時代も天才は数少ないが、多くは必要ない。
奴隷の扱いは酷烈をきわめた。機械の部品を取り替えるよりも簡単に補充がきくものだから、結果的に、たいていの企業が奴隷制度施行前よりも業績を伸ばした。機械労働革命期にあっては生産効率があまりに高すぎた半面、多くの人間は失業者で購買力がなく、ラインはたいてい止まっていたことを考えれば、資本家にとって奴隷制度は渡りに舟だった。「理想の人材とは人件費ゼロで働く者」とかつて揶揄まじりにいわれていたが、実現してみれば機械はそれ自体のメンテナンス以外に一切の消費を生まないので、夢の世界は到来していなかったのである。停滞していた世界経済の歯車が再度回り出し、官僚たちは政治家に「成果」を強調させ、資産家たちは金銀不動産に変えていた富をふたたび株券や債券に変換させはじめたが、強制労働に突き落とされた人々の不満はすぐにきな臭さを発するようになった。もちろん、あからさまに『奴隷』と呼ばれていたわけではないが、実質はまるっきりの奴隷だったわけで、さすがに、この前までは「人権! 人権!」と、ひとつ憶えに叫んでいたことを忘れたわけではなかったホモ・サピエンスさまがたは、事態の改善をはかり、『改正人海戦術基本法』によって晴れて奴隷制度は合法化され、奴隷は手厚く保護されることになった。一部の『奴隷頭』がその他大勢の同僚を虐げるような理不尽は消え、『奴隷』であれば完全な平等が実現した。『自由民』は、奴隷は『奴隷』だということがはっきりしたために、奴隷は、待遇が大幅に改善するということで、『奴隷保護法』こと『改正人海法』はさしたる抵抗なく受け入れられた。
そして現在、奴隷は全人口の七割ほどを占めている。
奴隷は気楽な身分だ。責任を負わされることは基本的にない。奴隷に必要な資質は、簡単な作業を就業時間中ひたすら続けるための、一定の根性だけ。資格を取ったりすれば奴隷でなくなることができ、それ自体はそんなに大変ではないが、おれはさほどがんばる気がない。だいたい、奴隷よりひとつかふたつ上のスキルがある程度では、『奴隷法』がなくなれば、やっぱり日雇い労働者以上にはなれない。社会体制がどうなろうと気にせずわが道を進める、なんて人間は、それこそ全体のひとつまみもいないだろう。おれ自身は奴隷制施行前よりマシになっているから、いいのだ。それが奴隷根性だ、といわれれば、それまでのこと。
そしておれは、今日もひたすらコンベア上へ荷物を載せていく。全長六キロに渡るコンベアの左右には、積み込み係の奴隷がいて、自分担当のトラックの荷台に放り込むべき荷物が流れてくるのを待っている。
ひたすら無言で、あるいは口笛を吹きながら、コンベアの騒音に抗して大声でくだらないことをしゃべくりながら、奴隷どもは休憩時間まで働き、休憩時間が終わればまた働き、定時がくればさっさと現場をあとにする。食事はいちおう食えるものが支給される。オフ時は、宿舎の中にも街角にも支給食券が使える店があるし、そうでない店で多少の贅沢をするのも、自炊するのも勝手だ。いわゆる『自由民』の中にも、『奴隷食堂』で済ますことで食費を節約しているやつがいて、『奴隷』の中にも、自炊で限界まで食費を切り詰め、支給された食券は全部金券ショップに売ってしまうというやつもいる。要するに、どの店で食っているからあいつは奴隷だとか、そうじゃないだとか、そういう区別はぱっと見ではつかないのだ。
昔の社会と、なんら変わるところはない。むしろ、『最低限の生活』が確実に保証された、かつてよりまともな世界になったのだ。
……と、おれは信じていた。いや、おれならずとも、そう思っていたやつは多いはずだ。
深瀬駿「事務室の女王」
彼女は灼熱の世界を背にして狭いエントランスホールの中央に立っていた。ビルの外では照りつける太陽がアスファルトを沸騰させていた。道路の向かいの、白亜のビルに反射して、網膜を焼くほどの強光がこちらに差し込んでいた。彼女はその逆光の中にいた。黒々としたシルエットが吹き込む風に揺れ、瞳の赤い虹彩だけが不気味な三日月のように、闇に浮かんでいた。
薄暗い廊下側から見ていた青年には、何か近寄り難い神像のように思われた。だがガラスの自動扉が音もなく滑り、風が止み、次いで彼の目が明るさに慣れると、そのイメージは跡形もなく掻き消えてしまった。そこにいたのは、ただの若い女だった。
「お久しぶりね」
彼女が呟いた言葉は、冷たい大理石に吸い込まれた。紛れもなく、数カ月前まで彼と同じオフィスにいた会計士の女であった。
「どうも」
青年が言った。二人は言葉も少ないままに、ビルの奥へと続く長い廊下へ、足を踏み入れた。このオフィスビルは周囲の建物を見下すかの如く、不遜なほど高くそびえていたが、来客を迎える正面入口は、彼女が通過した細やかなエントランスのみである。さらにそこから、窓も照明も無い、薄霧立ち込める廊下が一筋だけ伸びていた。廊下は床も壁も一面に、冷ややかな大理石張りだった。壁に近づいて息を吹きかければ白く曇り、手を当てればべったりと白い跡が残るほどに冷えきっていた。密度を増した空気が壁にそってカーテンのように降り注ぎ、床の表面に渦巻いていた。
「まさか出迎えてくれるとはね。今は業務中じゃないの」
二人の革靴が床を打った。辺りを覆う暗闇のどこからか、子供たちが内緒話をしているような、また同時に海鳴りにも似た、くぐもったさざめきが聞こえた。彼らが通り過ぎたところでは時折、壁に白い手形の群れがひたひたと現れては、すぐに霧消していった。それはまるで幽霊の集団が壁を手がかりに進むように、ひっそりと、しかしかなりの速さで這いまわっていた。
「僕の方は問題ありません。今の上司は予想していたよりもずっと、融通がきくみたいです。たまに社内をぶらついたりもできるんですよ。問題といえば、この廊下、何度通っても慣れないと言いますか……僕はどうも、この先にある……四十九代目の人事部長が、苦手、と、いいますか、次の角にある、棺なんですが……」
廊下の左右に並ぶ台座の上から、文字通り死んだ目で二人を見下ろすのは、アクリルの棺に葬られた、歴代社員たちだった。名誉の過労死を遂げた社員たちは、生前の装いもそのままに防腐処理を施され、アクリル樹脂の柱に沈み、その姿を永久に留めることになるのだった。殉職社員たちは皆、脳組織もその他の内蔵も失う事なく、この新しい技術によって不朽の棺と栄誉を獲得し、どことなくわざとらしい微笑を顔に貼り付けて眠るのだ。眠るとは言っても目は開いたままで、過労で焦点を失った瞳に、狂気的愛社精神を色褪せぬまま宿していた。
「自社製品が怖いなんて、妙な話だと思うけれどね」
すでに死んだ社員たちの、よれよれになったスーツ、シャツの襟元の汚れ、ペンだこ、カフェインと栄養剤に長年依存した末に咀嚼を忘れてしまった細顎、それらすべてが、その人が良き社員であり、良き社会人であり、理想的な人生を送ったことを示していた。
「中身は自社製品じゃないと思いますよ」
「そうかな、実質的にグループの傘下にある学校を卒業して、グループの会社に入って、そこで死んで。食べるものだってほとんど系列会社の商品だとしたら、頭の中身も肉体も、全部自社製みたいなものじゃない」
からかう会計士にはこれ以上耳を貸さず、彼は歩みを早めた。さっと通りすぎるんだ、さっと。意識しないように。
棺に使われるアクリル樹脂は、クリスタルガラスに匹敵するほどの透明度を誇っていた。廊下を満たす凍みるような空気と清水より透き通る樹脂、それらの屈折率の差が亡骸に生き生きとした瑞々しさを与えていた。
棺は所属会社と階級の順に並んでいた。廊下の奥へ進むにつれてより重要な会社へ。さらにその会社の、下級社員から幹部の順に。台座に嵌めこまれた真鍮のネームプレートが、この暗さでは判読しかねるほど小さな文字で、死者の人生を語り、生前の思想を代弁していた。
〈―愛社精神万歳! 創業家万歳! 資本主義万歳―〉