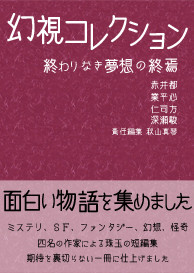水池亘「お返しにはペンシルパズルを」
意を決して扉を開けたというのに、彼女は僕の存在に全く気がつかなかった。黒髪を肩まで垂らしたその女性は、四畳半ほどの部室に一人きりで座っていた。足を組み、テーブルに頬杖をつきながら、右手に持った鉛筆で紙に何かを書き連ねている。
眼鏡の奥の、真剣な眼差し。
しばらくの間、僕は声をかけることができなかった。
だが、こちらにも一応、用事というものがある。
「……あの」
「ん?」
夢から引っ張り出されたかのような表情で、彼女は僕へ振り向いた。ストレートの黒髪がふわりと揺れる。
「新入生か。部活動の見学?」
「はい」
「ふうん。『美術館』をあえて紙の上で遊ぶことについて君はどう思う?」
「は?」
いきなり想像外の質問が飛んできた。
「『美術館』だよ。君も解いたことがあるだろう」
「あ、はい、それはまあ」
『美術館』は数あるペンシルパズルの中でも人気が高い部類に入る。たしかに、この部活に見学に来るような者であれば、知っていて当然だった。
「あのパズルはな、PCで遊んでこそだという意見が根強いじゃないか。だが私は、紙に直線を引きながらまったりと解く方が好きなんだ。そもそも十年前は皆そうして遊んでいたのだし」
「あの……」
「ただPCに移植されたことで発明者が全く意図していなかった解き味が生まれたという事実は、とても興味深いね。パズルが生き物であり、時代と共に存在することの証明だよ。このテーマについて、君の意見は?」
「え、ええと……」
話の展開が早すぎて、ついていけない。正直な話、失敗したかな、と思わないでもなかった。それでも、真剣に回答を考えてみることにしたのは、きっと彼女の声が凛々しさに満ちていたからだ。
「……ええと、コンピュータ上でペンシルパズルを解く最大の欠点は、ミスしたときに簡単に修正ができることだと思います」
「なるほど」
彼女は感心したように何回か頷いた。
「だがそれは、普通に考えれば長所だろう」
「ええ。ただ僕は、この機能がいくらか緊張感を失わせてしまったようにも感じるんです。間違えて入力してしまった丸印も、ワンクリックで消してしまえる。それどころか、解いた手順が記録されているから、アンドゥでどこまででも過去にさかのぼることができる。はたしてそれは、ペンシルパズルの面白さにとって、本当に有用な機能なのでしょうか」
「技術の進歩によって便利になることが、必ずしも良いことではない、と」
「はい」
僕のはっきりとした返事に、彼女はふふっといたずらっぽく笑った。そしておもむろに立ち上がると、棚の引き出しから一枚の紙を取りだした。
「これに名前を記入してくれ。提出は後日でかまわない」
その入部届けには、既に顧問の判子まで押してあった。
「君と話すのは楽しいよ。入部、歓迎する」
〈本編に続く〉
鳴原あきら「カインの神様」
部屋の扉を開けた瞬間、阿部正樹は「間違えました」と帰りそうになった。
非常勤職員の雇用切り替えの時期が近づくと行われる、職場相談の日だった。
一対一の面談で、今の仕事はどうか、何か困っていることはないか、配置に対して希望があるかを述べる。これはまったく形式的なことだった。同時期に行われる勤務評定によって、次回の半年雇用と時給が決まるので、ここで波風をたてる者はいない。
「ここであっていますよ、阿部さん。時間通りですね」
物柔らかい声に、阿部は振り返った。
窓を背にして座っていたのは、およそ市役所の一室にふさわしからぬ男だった。
白の三つ揃えを品良く着込み、淡いいろの髪が、二月の陽光にきらめいている。日本人離れした美貌の持ち主だ。すらりとした身体や肌の様子から、ずいぶんと若く見える。
「今まで、職場相談って、総務の偉い人がやってくれるものだったんですが」
長身をすぼめて、阿部は男の正面のパイプ椅子に座った。
謎の男は、名刺大のケースをデスクに置いた。「相談員 満潮音純」と書いてある。仕立てのいいスーツに、ネームプレートで穴をあけるのが厭だったのかもしれない。
「みしおね・じゅん、と申します。雇われ相談員です。職場相談にも、流行りのアウトソーシングの波が押し寄せてきたというわけです。上司と腹をわって話すのは、なかなか難しいことですから、こういうのも悪くないと思いませんか」
そういって、美しい微笑を浮かべる。
阿部はさらに身を縮めた。
「はあ」
「メモはとりません。ここでの会話は、職務上、他へは決して漏らしません。安心して、お話しください」
「はあ」
「資料を拝見しました。あべ・まさきさん、四一歳。勤続八年目ですね。以前は外資系企業にいらしたそうですが、今は主に、市役所のデータ入力の仕事を、非常勤で、ずっと続けてらっしゃる」
「ええ。以前はオーストラリアから食肉を輸入する小さな会社で、十年ほど貿易事務をやってたんですが、そこが倒産してしまって。三十過ぎでただの事務屋じゃ、ツブシがきかないんで、あちこちまわったあげく、市役所のバイトに応募したんです。ここは港町ですから、英語の入力作業もけっこうあって、そのままズルズル、総務の下請けみたいな感じで、八年もいるわけです」
「阿部さんは、正職員になろうとは思わなかったんですか」
「いや、正職員さんも、事務方は意外に給料、安いんですよ。いろいろ大変そうですし、それに先輩を差し置いて、試験を受けるのも」
「その年齢で、非常勤であることに迷いはありませんか」
「母と二人暮らしで、他に養う口もないんで。実家暮らしで、貯金もあるんで」
「では、現状維持をお望みということですね」
「はあ」
「まあ、それをとやかくいう資格もないのですがね。阿部さんより、いくつか年上ですが、やはり僕も、同様の身ですからねえ」
「ええっ、年上?」
阿部は思わず身を乗り出した。
「僕も若く見られる方ですが、まさか四十代の方だとは思いませんでした。ええと、ま……みしおねさん」
「まあ、本業は別にあるんですが、それはさておき、一応、職場相談の場ですのでね。職場に対する希望があれば、お伺いしましょう。現場の声として、吸い上げられるものならば、なるべくいい形で、上にお伝えしたいと思います」
「そうですねえ」
阿部はちょっと考え込み、
「先輩の時給を、五円あげることって、できませんかね」
満潮音は、虚を突かれた顔をした。
「五円、とは?」
阿部はうなずいて、
「二年前、役所の人間全員、英語の試験を受けろって通達があったんですよ。非常勤も含めて、指定した日にトーイックを受けろと。それで、僕も受けたんですが、英語を聞くのも久しかったんで、八〇〇点しかとれなかった。でも、それが年末、技能給として加算されて、先輩より時給が五円、あがっちゃったんです。でも先輩は、試験日に具合が悪くなって、受けられなかったらしくて」
「なるほど。それで、少々やりづらいと。しかし、そういう話でしたら、先輩が後日、あなたより上の点数をとればいいだけの話ですよね?」
「それがそうじゃないんです。試験制度は上層部の気まぐれみたいなもので、その年だけで終わっちゃったんです。それ以降は、個人的にどんな成績をとっても、関係なくなっちゃったんで」
「なるほど。しかしそれ以前に、英語ができないのに技能給を加算することは、不可能ではないですか」
「いや、先輩、できるんですよ。実務系の専門学校を出て、やっぱり農業系の輸入会社で働いてたっていってましたから。海外のお客さんが来た時なんかも、すすんで役所内を案内してますよ。僕なんか未だに不案内で、腰がひけちゃうんですが」
「そうですか」
満潮音は不思議そうな顔で、ファイルをめくった。
「あなたのいう先輩というのは、甲斐照海さんのことですね」
阿部は頬を引き締めた。
「個人情報は、漏らさないんじゃなかったんですか」
「あなたも知っていることしか、お話ししませんよ。かい・てるみさん。三三歳。最初に入った会社が二年で倒産して、それからここにきた。勤続十一年目で、あなたより三年早く入っているわけですね。しかし、八歳も年下の彼を、先輩とよびますか」
「おかしな話じゃないでしょう。甲斐さんは仕事ができますし、いろいろお世話になってますし。短期バイトの指導をしてるのは甲斐さんで、僕の方は、短期さんと同じような入力仕事や雑用しか、やってないんですから」
「そのようですね。あなたの直属の上司の園生幸司郎さんは三〇歳で、お子さんも二人いるのに、すでに窓際族扱いです。課長を二年もやっているのに、ほとんど仕事を覚えておらず、おかげで甲斐さんのいいなりです。総務に居場所がないので、データ入力課とあだ名された雑務専用の部屋に押し込まれ、あなたと甲斐さんと、短期バイトのいる前で、飾り物のように座っているだけです」
「いいすぎですよ。園生さんは責任者だから忙しいんです。上への報告も毎日のようにあって、だから非常勤まで手がまわらないだけです。その証拠に、席を温めてることなんて、ほとんどありませんよ」
言いつのる阿部に満潮音は、ふたたび美しい微笑で答えた。
「阿部さん。あなたは本当に、いい部下で、いい後輩ですね。僕は昨日、市役所の中を案内されている間、あなたが甲斐さんに大声で叱られているところを、偶然、見てしまったんですよ」
「あれは別に」
そこで阿部は口ごもった。
満潮音がいっているのは、阿部が入力した、扶養手当の書類のことだろう。
〈本編に続く〉
渡邊利道「シャーロットに薔薇を」
予定外の場所で目がさめた。
もちろん眠りが浅かったわけじゃない。本部からの命令で無理矢理眠りから引きはがされたのだ。
こんな覚醒には決まって悪夢がつきまとってくる。
コールタールのような闇に身体が絡めとられ空間の奥底に引きずり込まれる。闇に溺れる夢。チラチラ火花が散って飛び、ゆったりと闇に飲み込まれていく。息がつまる。喘ぐ自分の声がどこか遠くから聞こえる。声が聞こえるってことは空気がある証拠だ、そう思って少し落ち着きを取り戻す。でも身体中にまとわりつく恐怖はまるで物質のように具体的で厚みがあった。
目を開いてもしばらくは覚醒したことに気づかない。無愛想な船室のなかで強ばった身体は汗だくになっていた。
苦笑が漏れる。
水平になったGシートから身を起こして、網膜スクリーンを起動させた。もちろん寝たままでも見られるのだが、覚醒後は出来るだけ身体を動かしたほうがいい。ポストに本社からの新しいメッセージが点滅している。予定を変更してある宇宙ステーションの捜索に向かってほしい旨が簡潔に述べられていた。希望するとあるが実際には命令だ。
添付ファイルにその宇宙ステーションのデータがあり、船のメインコンピュータで解析して必要情報を表示させる。
ごく、短いタイムラグ。
夢は変化した周囲の重力に身体が鋭敏に反応したものに違いなかった。船外モニターをチェックするとそこにはいつも変わらぬ漆黒の闇があり、もしかすると俺はいつもその闇の中に自分が放り出されてバラバラになるのを夢想していて、何かのおりにその願望が夢になって現れるのではないかなどと考える。そしてまた無駄によくできた身体に笑ってしまう。
この身体は自前のものではない。会社が用意した宇宙探査に特化した人格データ用の義体だ。
俺のオリジナルは、かつて太陽系外縁を根城に惑星探査会社を経営していたベンチャー会社の経営者だった。宇宙開発が最先端だった時代はとうの昔に去って、いまや宇宙はヤバい仕事の掃き溜めだ。人類が認知している空間距離はこの百年ほどで気違いじみて拡大し、無人探査機ははるか隣接する恒星系にまで出立しているものの、実際の生活圏となっているのはその九十九パーセントが木星の公転軌道の内側にとどまって長大な停滞期に陥っている。数十年前に起きた政治的分裂は年を追うごとに深刻化し、あらゆることが疲弊し弛緩して地球文明の黄昏気分はいや増しに増している。かつてエッジワース・カイパーベルトやオールトの雲がフロンティアだった時代には、宇宙生活者たちはエリートであり、英雄ですらあったのだといっても、もはや誰も信じない。漆黒の闇はまったき虚無をしか現していない。
もっとも俺のオリジナルにとっては、その虚無に金がじゃんじゃんうなりをあげて渦巻いているように見えたらしい。ノマド式オフィスをかまえ、何体ものみずからの人格データのコピーを生成・駆使し、複雑な重力計算が必要な小惑星帯やプラズマの嵐吹き荒れる太陽近くの宇宙空間の探査を一手に引き受けて敢行し、そうやって取得した情報を取りまとめて上部企業に売るという業務内容で、ちょっとした業界の寵児とでもいった存在になった。
オリジナルが何を考えていたか、どういう人間だったかというのは俺にはまったくわからない。
そんなこんなで一世を風靡したが、深淵はすぐ足許に開けていた。コピーをとるだけならまだしも、そのコピーの体験をレポートだけではなくみずからの体験として吸収するために再統合をくりかえした結果、彼の精神は人知れず不安定化の一途をたどっていたのだ。P‐18と命名された俺が生成され探査宇宙船にダウンロードされて水星航路を出発したきっかり約十八時間後に、判断ミスによる投機の失敗から連鎖的に資金繰りが発火、炎上し、実に三十分ほどですべての資産が債権者に差し押さえられた。顧問弁護士の対応は早く、すぐにオリジナルの精神状態の悪化を申し立て、事業資産のみを放棄して個人資産については免責されそのまま月にある精神療護施設に引き蘢ることで決着をつけた。
そして俺は債権者に差し押さえられたってわけだ。
幸いなことに、会社は俺を処分しなかった。それどころかオリジナルがあてがった以上の高スペックの義体と探査船をセットに再構成し、宇宙探査の業務を続行させてくれた。もっとも、だからってそいつは感謝しなけりゃならないようなことじゃあない。端的に言えばそいつは会社にとって体のいい奴隷を一個手に入れたようなもんだからだ。
どうやら地球のほうではデータ人格にも人権を認めようなんて動きがあるらしいが、もちろん宇宙の果てにそんな発想はなかった。借金の形に売り飛ばされた女郎よろしくぶっ壊れるまで休みなく稼働し続けるのが俺の運命だ。報酬と言えば腹いっぱい飯を食うことと、義体と探査船のスペックを充実させること。自分でも驚くほどに宇宙空間に対する知的好奇心、探究心なんてものは一切合切持ち合わせてはいなかった。宇宙は巨大な冷感症の女みたいで、退屈ながらんどうだ。この無限に続く空虚な沈黙にやられてしまわないためには、ナルシシズムでやわらかく自我をくるんでやる必要があるのだ。俺は覚醒するたびに義体と探査船をひとわたり確認する。おそらくこのクラスの小さな船体では外縁系でも随一の状態に保持されているはずだった。無駄な機能は一切なく、どんな予測不能な事態にでも素早く対応できるに違いない船の状態と、まったく生身の人間と同じように見えてしかし苛酷な宇宙空間で自由な作業を可能にする最新鋭の義体。テクノロジーが俺の怪しい自我を生温かく慰撫するのだ。テクノロジーは未来を無思考の夢に置き換える。
もっとも宇宙を冷感症の女と言ったが俺に性欲はなかった。オリジナルの生活史の記憶もない。無意識といえるような領域はほとんど縮減されていて、機械の操作手としての判断機能さえあればそういった人間的な「精神」は必要ない、というかむしろ宇宙で生活するには有害でさえあるからだ。しかしケミカルな代謝機能を機械的に再現しているだけとはいってもそこはやっぱり「人間」で、俺の思考はとめどなく流れていく。執着する。薄っぺらな自我がデータバンクとセンサーの表面にこびりついているみたいな「人間性」。そんな滓みたいな「精神」に過ぎないとしても、というよりもむしろ、そういう薄っぺらさが宇宙の沈黙の中で勝手にざわめきはじめ、そこには何にもありゃしないってのにテクノロジーで作り上げた壁をのりこえてどこからか隙間を探して深淵を覗き込む。オリジナルは自己を分裂させすぎて狂気に陥ったわけだが、ケーキの一切れみたいにナイフで取り分けられた俺は、宇宙の胃袋に放り込まれて溶かされるのに抵抗して固く石にでもなるしかないと思いながらいつか亀裂が入って粉々に砕け散ってしまうんじゃないかってずっとおびえているわけだった。
恐怖にどっと汗をかく。
義体のくせに、記憶の厚みをいっさい有してないくせに心理的な引き金に敏感に反応する面倒な身体は、たまに受けさせられる会社のメンテナンスを担当する技師によるとそれこそがいわば無意識の機能を果たしているのだそうだ。夢を見ることも身体の無意識的機能の一つで、そうやってだらだら汗をかいたり無駄にドキドキ鼓動を激しくしたりしているからおまえは狂わないでいられるんだよと脂でテカった顔を歪めて技師は言ったものだった。同情してるんだか挑発してるんだかわからないようなにやけ顔のあいつは、しかし義体だったんだろうかそれとも身体までまっとうな人間だったのかあるいはサイボーグか。一度聞いてみたいと思いながらついそのままになっていた。たぶん今度の任務を終えたらまたメンテに出されるだろうから今度こそ聞いてみようか。
〈本編に続く〉
泉由良「微笑みと微睡み」
駅の中にあるカフェは、凹凸のある厚手のギフト用ボックスで出来ている。
駅自体はこの街で一番大きな建物だ。否、駅の中に街が造られたのだろうか。もし旅人がそれを誰かに尋ねるとしても、彼は答えを得ることはないだろう。誰もそんなことは気にしない、とくにこの街に─あるいはこの駅に─住む者たちは。
過度に装飾的な、硝石と砂と鉄筋で造られている古びた正面から、無数の細道と小さな店─大抵は閉まっているが─の入り組む迷宮に入れる。上手くやればプラットホームに出られるかも知れない。まるで骨董屋の倉庫の一番奥で、売却予約済みの札だけ掛けられたまま忘れ去られたような駅。
優雅なカーヴを描く屋根の下から定期的に混雑が吐き出され、駅前の大きな広場を横切ってゆっくりと拡散してゆく光景を見ると、それでも列車はダイヤに沿ってやってきて、人々は乗ったり降りたりしているのだなとわかる。信じ難いけれど仕方がない。乗ることと降りることの違いとは何だろう。彼らは何処からきて何処へ向かうのだろう。
この物語はこの駅の中の街に始まる。
物語、と云う言葉の危険性を敢えて信じて─(だって、似ているだろう? 物語り、とか、もの憑き、とか)
ここにあるのは例えば割れたティーカップの、破片で成されたモザイクのようなもの。決して、カップの姿そのものではない。表れなかった破片もある。それを忘れないで(書き留めておいた方がいいかも知れない)
紙製のオーディオ・セットが(きみは本当に紙が好きだね)黒いレコードをくるくると回し始め、私は駅の中のそのカフェでいつものように遅い朝食を摂っていた。トーストとバタ、プリーツレタスとトマトのサラダ、珈琲を一杯、そして果物。この日はキウイ。
キズナがいってしまった日から何日が経っていたが、実際に何日後だったのかはわからない。
手風琴を抱えた陶子が、ゆで卵と塩の小瓶をのせた皿を持って、私の向かいに座りにきた。陶子は歌手だ。時々ここのカフェでも歌っている。
「見た?」
陶子は挨拶をしない。
「おはよう。何を?」
「知らないの?」
陶子はほっそりとした指先で、卵の殻を剥くことに気を取られている。あまりに不器用なので私は手を伸ばしてそれを取り上げ、つるりと剥いてやった。陶子の注文するゆで卵は決まって固茹でだから、剥き易い。
「ごめんね、この指は楽器しか操れないの」
陶子は悪びれずに微笑み、話を戻す。
「知らないのね。あれの残骸」
「残骸?」
私は少しこわばった声になって問い返す。
「なんて云うのかしら、このあいだのあれ。千咲さんのお友だちが乗っていたのでしょう?」
「……気球のことね」
私は珈琲の残りをのみ干した。
「キズナ、落ちたの?」
「知らないけどその、気球の残骸が見つかったそうなの。これを食べたら一緒に見に行かない?」
私は陶子の落ち着いた口調に微かに苛立ちを感じながら、卵を齧る彼女を見つめた。
全く、陶子は綺麗な娘だ。
例えるなら彼女は、幾時代を経ても常にその良さが見い出されてきた幸運な美術品のようだ。いつだったかは忘れてしまったが、初めて彼女を見たとき私は、まるで私だけの素敵なお人形に街角のショウウィンドウで出くわしたような、一種感動的な心持ちさえ感じたのだった。
キズナの気球は黄色かった。象徴的に黄色かった。そう、イェローサブマリンの面影。
昼過ぎの空はとても眩しくて、バーナを扱う彼女の表情は見えなかった。駅前の広場は気球を見物するひとにあふれかえっていたから、たぶん彼女も私を見つけられなかっただろう。おいてけぼりの、ひとりぼっちの私。
私は手も振らずにつっ立って、黄色い気球を見上げていた。
あの気球はキズナが自分で組み立てたものだ。私たちの家の庭で。私もほんの少しだけ手伝ったが、殆どは座り込んで、紅茶をのみながら見物した。彼女はどうやって作り方を知ったのか、傘の骨を折り曲げて枠組みを作り、気体燃料を調達してきた。発熱装置はアルコールランプを試したあとでガスバーナに変えた。バルーンの下に吊り下げる巨大なラタンの籠の中で手際よく作業をしていた彼女は、鳥かごの中の鳥みたいに見えた。或いは、柵の中の子どもみたいに見えた。
気球が完全に浮かび上がると見物人たちは歓声をあげ、周囲の建物にはどの窓にも好奇心に満ちた顔が覗き、屋上に集まった人々は口々に何か叫びながら指差していた。その騒ぎは無論まったく気球の珍しさのせいばかりではなく、街を出ようとする稀有で向こう見ずな若者に対する意見、好奇、同情、羨望、忠告などが、いちどきにその場で交わされていたためだった。
キズナは真剣に─姿は見えなかったけど、おそらくは─バーナの炎を調節し、気球は私が思っていたよりずっと速いスピードで、すべらかに飛び去っていった。私はそれが小さな点になって、やがて見えなくなるまで見送った。さようならキズナ、と。
何日前のことなのかはわからないし、何曜日だったのかもわからない。この街でそれを知ることは、三つこぶ駱駝を見つけようとするくらいの難題なのだ。
でも、あれは日曜日に似ていた。そんな気がする。
〈本編に続く〉